「早く秋になってほしいものだね」という表現には何の説明も必要ないと思いますが、「命あってのものだね」という言葉の語尾に使うものだねを物種と書くということは意外に知られていないようです。「物だ+ね」ではありませんので、「命あってのものだねぇ~」という書き方(声の出し方)をしてしまうと誤りということになりますね。
「命あっての物種」という諺

命あっての物種(ものだね)は諺。物種には「物事のもととなるもの」という意味があります。
命あっての物種(ものだね):
どんなことも命あればこそ出来る。
命を軽んじることなく、まずは生きることを選び、
大切にしていこう
頑張りすぎてしまう人が周囲にもいるのではないでしょうか。そんなとき、私たちの多くは「無理をしないようにね」という月並みな言葉しか浮かばなかったりするものですが、こういう諺を用いて先人の知恵を伝えてみるのもいいかもしれません。
「あした咲くための今日の命、今日の種だよ。命あっての物種、休むことだって大切」
物種は季語でもある
命あっての物種と同じ意味の言葉に「命に過ぎたる宝なし」「死んで花実が咲くものか」というものがあります。また、種という言葉からもわかる通り、「これから」を連想する物種は春の季語でもあります。
ものの種にぎればいのちひしめける / 日野草城
種は静的な存在ではありますが、大きな可能性・エネルギーを秘めています。爆発前夜、夢を見ることが出来るのも今日の命あってこそ。どうかそれぞれの「物種」を大切にしてほしいものです。


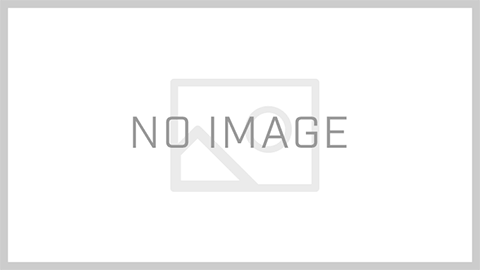



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
