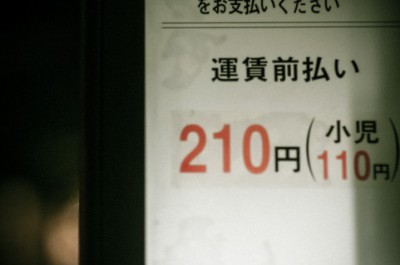雰囲気の良いお店などを見つけたとき「あのお店は敷居が高すぎて入るのを躊躇してしまう」という表現をすることがありますが、これは誤用。「敷居が高い」という言葉は誤用ランキングのワースト3にも入ると言われていますので、今回は「敷居が高い」という言葉の正しい使い方についてまとめてみます。
(2018年1月追記)
なお、2017年12月に発売開始となった広辞苑 第七版では、この記事で書いてある「敷居が高い=入るのを躊躇する=誤用」という考え方を取っていません。誤用である、誤用ではないという考え方については今後、急速に変化していくのだと思いますが、「誤用だ」「誤用というのが誤用である」という変遷も含めて紹介したいと思いますので、本文内は執筆当時のまま手を加えずにしてあります。文末に追記していますのであわせてごらんください。
「敷居が高い」には分不相応(自分には合わない)の意味はない

「自分のような庶民に、あの高級店は敷居が高すぎる」「この資格に挑戦するのは、自分には敷居が高い」と、「敷居が高い」を「自分には合わない(分不相応」」「レベルが高い」という意味で使うのは誤りです。
「敷居が高い」は
義理を欠くことやご迷惑をおかけするようなことがあって、その家に行きにくいという意味
「敷居が高い」の正しい意味は義理を欠いたりご迷惑をおかけして、その家に行きにくいこと。たとえば、恩師に何の近況も知らせないまま数年が経ったときや、お世話になった方に御礼もできないまま御無沙汰をしてしまったとき、物を借りて返せないまま時間が経過したときなど、相手の顔を見て声を聴きたくても連絡をするのに躊躇してしまうことがありますね。そういうときに使うのが、この「敷居が高い」という表現になります。
「自分には合わない、難しい」は何と表現するべきか
では、「敷居が高い」の誤用である「自分には合わない・難しい」という意味で表現したいときには、どんな言葉を使うべきでしょうか。
「自分には合わない、難しい」を表現したいときは
「ハードルが高い」「レベルが高い」「分不相応」を用いる
ハードルが高い、レベルが高いという表現、そして分不相応という言葉を用いるようにすれば、本来の正しい意味で伝わるようになるでしょう。ハードルやレベルが高いというカタカナの入り混じった表現は、受け取る相手によって(主にご年配の方)は嫌悪感を示される方もいます。状況によって表現を使い分けられるようでありたいですね。
「敷居が高い」は特に30代以下で誤用が多い言葉
文化庁の実施している国語に関する世論調査によって、この「敷居が高い」は30代以下で誤用が多いことがわかっています。

40代を境に,50代以上では本来の意味である「相手に不義理などをしてしまい,行きにくい」,30代以下では「高級過ぎたり,上品過ぎたりして,入りにくい」を選んだ人が多くなっています。
50代以上の方は「敷居が高い」という言葉について正しい理解をされている方が多く、30代以下の方は誤った認識をされている方が多い。まさに言葉の意味が変化しつつあるタイミングであるといえますが、いつもお伝えしている通り、表現力は思い遣り。自分の知っている知識で相手を攻撃するのではなく、相手によって使い分けをしたり、相手の誤用を自分の理解のなかで変換して受け止めるようにして、優しさに満ちたコミュニケーションを図るようでありたいものです。
広辞苑 第七版では「敷居が高い」の意味が改められた
2017年12月に発売開始となった広辞苑の第七版では「高級だったり格が高かったり思えて、その家・お店に入りにくい」という表現が付け加えられました(第六版まではこの表記はありませんでした)。
また、注目したいのはその表現で、「(1)不義理または面目ないことがあってその人の家に行きにくい (2)高級だったり格が高かったり思えて、その家・お店に入りにくい」と順序をつけることなく、あるいは「不義理または面目ないことがあってその人の家に行きにくい 〈俗説〉高級だったり格が高かったり思えて、その家・お店に入りにくい」と「俗に言うには」という言葉を用いずにこの意味を紹介しているところです。
つまり広辞苑では、「敷居が高い=高級な感じがして入りにくい=誤用」であるという考え方は一切認めず、これは正しい使い方であるということを認めるようになりました。言葉の意味、使われ方は変化をしていくものですが、2017年に、このような明確な変化があったということは興味深い事実だと思いますので、この段落を追記しておくことにいたしました。
辞書だって変化する! 「敷居が高い=高級そうで入りにくい=誤用」の意味が広辞苑第七版では改められた!
言葉の意味は時代によって変化します。意味を説明する辞書の表現も改められて当然。広辞苑の第七版では「敷居が高い」の説明に変化がありました。敷居が高い誤用説について広辞苑はどう考えたのか。興味深い変化をご覧ください。
なお、コトバノでは、「敷居が高い 誤用」で検索してこられる方が多いので、あえて、本文内容、見出し、タイトルなどは変更しない方針にしています。