古文の授業でならった「べし」という言葉は、今日でも、意志や教訓を表す文章に用いられることがよくあります。
「人の話を聞くべし」という使い方であれば問題ありませんが「人の話を聞くべき」という用い方をすると誤りになってしまいます。「べき」という耳にすることの多い言葉の用い方について説明します。
文末に「べき」を使うとなぜ誤りになるのか、その理由

「べき」という言葉を文末に用いることは誤りです。
「べき」は「べし」の連体形。
連体形を文末に用いることは(原則として)できない
「である」「だ」「です」という言葉をつなげて使う
「べき」という言葉は「べし」の連体形なので文末に用いることはできません。べき、で文章を止めたいときは、そのあとに「である」「だ」「です」という助動詞を用いるのが原則です。
たとえば「あなたは毎日努力するべき」というのであれば「あなたは毎日努力するべきだ」と言葉を繋ぐ。「話を聞くべきという意見」であれば「話を聞くべきだという意見」という風に用います。
| 基本形 | 未然形 | 連用形 | 終止形 | 連体形 | 已然形 | 命令形 | 活用の型 |
| べし | べく・べから | べく・べかり | べし | べき・べかる | べけれ | 〇 | 形容詞ク活用 |
助動詞の「べし」には推量・意志・当然・適当・命令・可能の意味がありますが、その活用形である「べき」は日常的に用いられるので、つい文末に用いてしまいがちです。
「連体止め」「体言止め」という表現もあるではないか、だから誤用ではないだろうという意見もあるかもしれませんが、名詞で文章を止める修辞方法は、余韻を与える効果を狙って行うもの。特に余韻の効果を狙う必要がない場面で用いるのは、やはり適切でないと考えた方が良いでしょう。
文末は「べき」で止めない。「べきだ」「べきです」「べきである」という表現にする。または終止形である「べし」を用いると覚えておいてください。
でも実際は「べき」で止まっている文章もよく見かけるような?
文末を「べき」で止めている文章は良く見かけます。これらはもう、一般化していて誤用ではないと言い切っている意見もあります。
歴史的な経緯でいうと、戦後に作られた国語審議会の公用文作成の要領(*pdf)では「べき」「べし」の使い方について言及があり、その流れを受けて作られたメディア(プレス)向けの用字用語集「記者ハンドブック」でも、文末をべきで止めないという項目があります。
「べき止め」が時代の変化に伴って一般化し、認められつつはあるけれども、教科書や役所、出版などの公的な場所ではまだ、この「べき止め」は許容されていないというのが実際のところでしょうか。
「べき止め」に違和感を覚える人もいる現状では、やはり、「べきだ」「べきです」「べきである」という表現にするよう意識することが無難であると言えそうです。

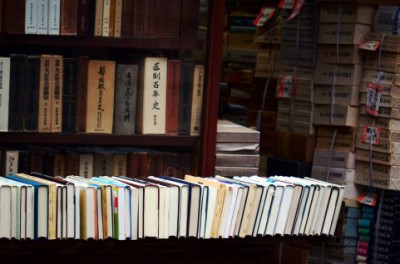



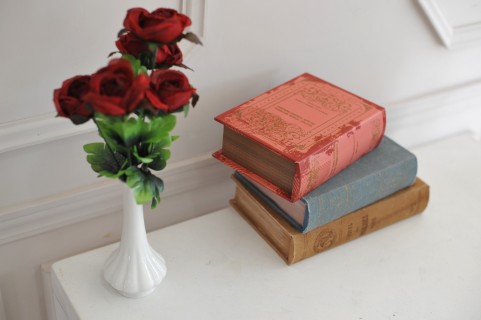
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
