暑中見舞いや残暑見舞い、お中元を先方が喪中のときに送るのはマナーとしてどうかということがよく問題になります。暑中見舞いや残暑見舞いは、心痛の相手に対して送るべきではないのでしょうか。送るとすれば、どのような配慮が必要なのでしょうか。
暑中見舞いや残暑見舞い、お中元は喪中のときに送っても問題ない

結論から言うと、暑中見舞いや残暑見舞い、お中元は相手が喪中のときに送っても問題ありません。
暑中見舞いや残暑見舞い、お中元は喪中のときに送っても問題ない
暑中見舞いにしても残暑見舞いにしても、暑さ続くなか、相手の体調を気遣って送る「お見舞い」ですので喪中の時期に送っても失礼にはあたりません。むしろ、大切なご家族を亡くされて気落ちしている方を慰めるような一文を添えて送ると喜ばれることでしょう。
喪中の相手に暑中見舞いや残暑見舞いを送るときの文例としては、
「(故人のお名前・敬称)を偲ばれながら、心寂しい日々をお過ごしかとお察し申し上げます。暑さの続く毎日ではございますが、ご家族の皆さまの健やかで穏やかな時間の続きますよう祈念しております。どうぞご自愛くださいませ」
という風なものをベースとして、相手との関係に応じて内容を変更すると良いと思います。
また、添える文には「ご冥福をお祈りしております」「お身体をご自愛ください」と書かない方が良いということを以前、ご紹介しました。


特に「ご冥福をお祈りします」という表現は、相手の宗派信仰によっては大変失礼な意味になってしまう可能性がありますので注意してください。暑中見舞いや残暑見舞いを送る時期についても、もう一度確認しておきたいですね。
お中元を贈るときに気を付けるべきこと
相手が喪中のときでも暑中見舞いや残暑見舞い、そしてお中元は送っても問題ないということについて説明してきました。
ところで、宗派や地域によって考え方は異なりますが、多くの場合、四十九日が終わるまでは忌中ということになっています。この時期は法要なども続いて慌ただしく、また、忌明けまでは人との交流をできるだけ避けるべきであるという考え方をすることもありますので、暑中見舞いや残暑見舞い、そしてお中元は四十九日が終わった以後送るようにした方が良いでしょう。
相手が喪中の場合にお中元を贈っても問題ありませんが、その場合、紅白の水引は使用せず、白の奉書紙をかけるようにします。熨斗には「お中元」と書かず「暑中見舞い」「残暑見舞い」と書いて贈るようにしてください。


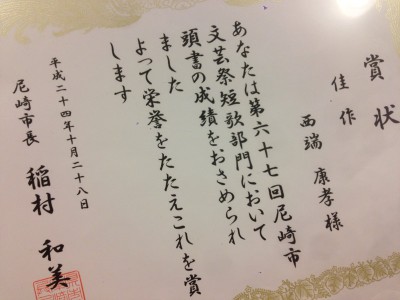

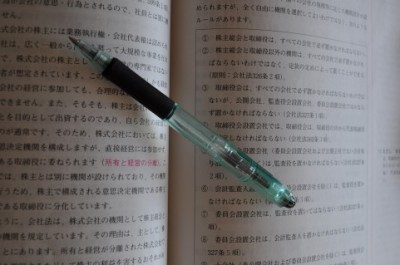

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
