以前「アンデスメロン」という名称は実はダジャレだったということを紹介しました。

また、日本語の雑学! 一から十までを声に出して読むときに起こる不思議現象とは?や日本相撲協会の住所は日本人ならどうしても間違えやすい漢字であるという雑学という話題も紹介しましたね。口承されるものもあれば形からおこった文字もあり、その意味の発生や過程で今となっては興味深いものとなった日本語の雑学もたくさんあります。今日はそんな日本語の雑学から「鳩(はと)」「鴉(からす)」「蚊(か)」「猫(ねこ)」という字の由来について紹介してみます。
日本語の雑学:「鳩(ハト)」「鴉(カラス)」「烏(カラス)」という字の由来について

鳩(ハト)という字は中国由来。動物の鳴き声というのは言語圏によって聞こえ方も違うそうですが、どうやら同じアジアに住む私たちはに大きな違いはないようです。鳩の鳴き声を思い出して想像してみてください。
鳩(ハト)はクックックと鳴くから鳥の横に「九」という字を用いるのが字源
鳩(ハト)の鳴き声はクックック、だから「九」という字が部首になっているのが字源であるというわけです。同様にカラスの鳴き声も想像してみてください。どんな風に頭の中に響いてくるでしょうか。
鴉(カラス)はガーガーと鳴くから鳥の横に「牙(ガ)」という字を用いるのが字源
鴉という字も同じ考え方。カラスの鳴き声がガーガーなので「牙(ガ)」という字を用いるようになったわけです。また同じカラスでも「烏(カラス)」という字は音ではなく、カラスの姿を字源としています。カラスは真っ黒なので目が何処にあるのかわからない、ならば「鳥」という字から一本線を取ってしまって(目にあたる部分を奪ってしまって)烏という字にしようと成り立ちました。
日本語の雑学:「蚊(カ)」「猫(ネコ)という字の由来について
ここまでの考え方と同じような考え方になりますが「蚊(カ)」は鳴くのではなく、ブーンと飛びますね。蚊はそのブーンと飛ぶ様子が字源になります。
蚊(カ)はブーンと飛ぶので「文」という字が虫の横に来る
また、猫(ネコ)という字はケモノ編の横に苗(ナエ)があります。苗という字は中国語で「ミョウ」と発音するので、これもやはり猫の鳴き声を字源としていることがわかります。
猫(ネコ)の字の中にある「苗」の中国語読み「ミョウ」が猫の鳴き声を表している
漢字の成り立ちを学ぶとき、私たちは一番最初に「山」や「川」というモノの形を由来とするものから覚え始めるため、意外に「音」を由来とするものを知らないことが多いようです。日本語や表現力に興味関心を持つには、こんな雑学から始めてみるのも良いかもしれませんね。

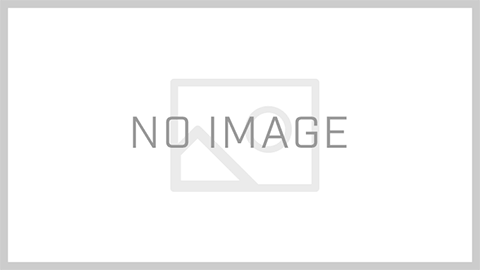



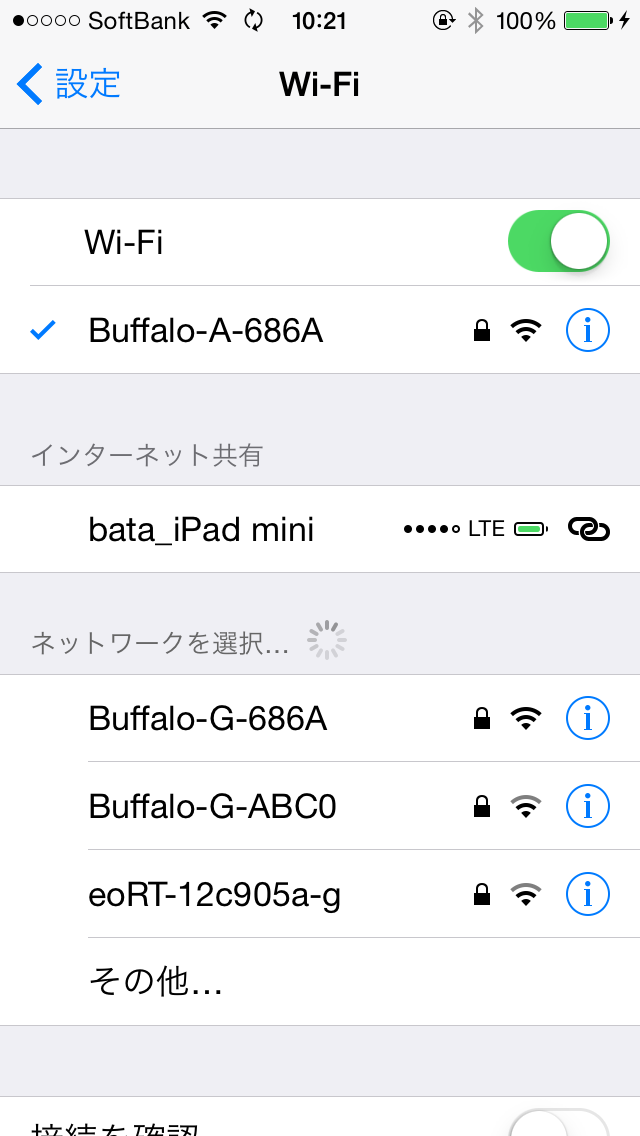
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a4cda69.cfef5cc5.1a4cda6a.e3f6f266/?me_id=1245295&item_id=10001782&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Filbelletto%2Fcabinet%2Fbnd5n_2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
